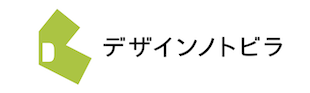ユーザーとの接点や好循環が生まれはじめている
――奥村さんと項さんは受賞からそれぞれ1年~2年経ちますが、作品に関する最新トピックがあれば教えてください。
奥村:まずWebサービスの方は、AIなども組み込みながらどんどんアップデートしていて、ユーザー数も当時の月利用者3,000人から5,000人まで増加しています。あとは、Webサービスだけでなく制度や仕組みに働きかけるような活動にも積極的に取り組むようになりました。
受賞をきっかけにメディアにも取り上げていただき、活動が広がるなかで助成金を受けたり、講演会に登壇する機会も増えてきました。
活動の内容自体についても、オンラインだけでなくオフラインの奥行きが出るようになってきています。支援という言葉から連想される枠にとらわれないイベントをやろうと思って、音楽ライブを開催したり、焚き火イベントを実施したりといった活動にも取り組んでいます。
 音楽ライブの様子。家庭環境問題や支援のことを考えずに、ただ楽しむ場をつくるイベント。少年少女たちの次の一歩に繋がるようなアーティストとの出会いの場でもある
音楽ライブの様子。家庭環境問題や支援のことを考えずに、ただ楽しむ場をつくるイベント。少年少女たちの次の一歩に繋がるようなアーティストとの出会いの場でもある
奥村:それができるようになったのは、支援してくださるメンバーやボランティアの方が増えてきたから。かつてサービスを利用してくれていた子どもたちが高校生や大学生になって、「ボランティアをやりたいです!」と連絡してきてくれることも徐々に増えているんです。こうした循環を続けていければいいなと思っています。
猪村:そういうお話を聞くと私も勇気づけられます。まさに自分たちもいま関わっている子どもたちが小学生から中学生くらいの年齢です。そうした子どもたちが、これから数年経って病気とともに生きていく過程で、その道のりは決してうまくいくことばかりではないかもしれないけれども、それでも、どんなときもその子らしさを大切に人生を歩んでいるような姿を見られたらいいなと思います。そのサイクルが生まれていくことをすごく楽しみにしています。
項: 私は、先ほども言ったようにクラウドファンディングを実施していましたが、消費者向けにPR文を書いたり、広報や宣伝に取り組んだりするなかで「デザイン作品をプロダクトとして世に出すこと」の難しさを実感しているところです。
あとは、2024年12月にクリエイティブ・メディアの「知財図鑑」が実施している「知財番付2024」で創造性部門賞(銅賞)を受賞できたのも大きな出来事でした。そこで、技術を活かして新たな可能性を切り開くものづくりに取り組む方々とつながることができ、私たちが使用するバイオ素材の可能性を、改めて実感する機会にもなりました。また、この道の先輩方から多くを学ばせていただくこともできました。

項: これまでは、「MYMORI」という作品や菌糸体という素材を今後どのように発展させていくか、自分でも想像がつかない部分もありました。ですが、さまざまな出会いやアドバイスを通じて、自分が歩んでいく道が明確になってきたように思います。「知財番付2024」はニューホープ賞での実績を見ていただけた賞だったので、ありがたく感じています。
奥村:私ももともとプロダクトデザインを学んでいたので、学生時代の作品を販売まで持っていくことの難しさと、それに取り組んでいる項さんのすごさがわかります。大学でプロダクトを学んでいる学生のロールモデルになってほしいなと思います。
項: ニューホープ賞の受賞後に、大学の指導教員から「生産するのは簡単だけど、実際に売っていくのが一番難しいよ」と言われたことを思い出しました。いままさにそれを実感しているところです(笑)。
潜在的な課題に対する価値創造をいかに広げていくか
猪村:最近、近しい領域で事業に取り組んでいる友人たちの話を聞いて思うのが、客観的に見たら課題に思うようなものでも、その当事者のお子さんやご家族にとっては、それが“いま”の姿であり日常だからこそ、実は課題として認識されていないことがあるということです。Child Play Lab.や第3の家族の出発点も近しい部分にあるのではないかなと思っています。
いわば、課題として社会が気付く前の「潜在的な課題」。自然な形で当事者と出会い、何気ない関わりの中で潜在的な課題を解決していくという過程やそのアプローチがとても重要であり、デザインの力もまさしく活きてくると感じます。その一方で、こうした課題やアプローチはとても曖昧なものだったりもします。顕在化した課題に対するわかりやすい解決策であればあるほど、社会からの共感は得やすい傾向にあり、ある意味ジレンマであると思っていて……ぜひふたりの意見を聞いてみたいと思っています。
奥村:それこそニューホープ賞が評価するものは、潜在的な課題に対する価値創造であるものが多いのではないかと思います。これからはそうした視点が重要になってくると思いますが、まだ現状は、何かの事象が発生したあとに仕組みが変わることの方が多いですよね。

奥村:そこに対する違和感を覚えている上の世代の方々もいるから、時間はかかりそうだけど、一緒に考えながら社会を変えていく過程にあるのかなと思います。
私たちは従来の支援的なアプローチではなく、自然な関わり方を重視することで、「潜在的な課題」の立場にいる子どもたちに向き合っています。オフラインのイベントもそうですし、オンラインでは検索上位で第3の家族にたどり着いてくれるようなサイト設計にも取り組んでいます。猪村さんはどうしてますか?
猪村:私たちは、事業として解決していくべき子どもとそのご家族が抱える課題の現状把握に向き合っているところで、ソリューションとしての訴求はまだ大々的にはしていないのが現状です。そのため、なかなか一般的なサイト検索で辿り着くのは難しいと思いますし、届けたいお子さんやご家族が置かれている状況としては、知ってくれたとしても心理的に申し込みまでの一歩が踏み出しにくい状況だと捉えています。
最近は、実際に伴走しているお子さんの闘病仲間に紹介いただいたり、病院の先生や看護師さん、保育士さんが直接紹介してくださることによって、少しずつお子さんとの出会いを増やしています。今日も師長さんの好意で病院にチラシを掲示してくださるとのことで、挨拶にうかがってきました。一人ひとりとの関係性を丁寧に育んでいきたいと思っています。

奥村:項さんも「消費者向けのPR文を考えている」と先ほど言っていましたが、言葉が重要であると私も感じています。いままでずっとデザインの勉強をしてきたので、福祉系の人に対してもデザイン系の言語で喋ってしまっていたんです。
だんだん福祉の言語もわかってきたけれど、逆にそっちに寄りすぎるとデザイン系の領域でコミュニケーションが取りにくくなったりもして。行ったり来たりしながら試行錯誤しているところです。
多数の視点を揺れ動きながら進んでいくこと
奥村:これまでの話を踏まえて、学生時代といまの自分で変わったことがあるかをみなさんに聞いてみたいです。私はいままでは本当にデザインが大好きだったけど、最近は福祉や経営のことも学ばないと進んでいけないことに気づいて(笑)。でも本当はずっとデザインだけやりたい自分もいたり……その狭間にいるんですよね。
項: その気持ちはすごくわかります。クラファンをはじめたことで広告について勉強したり、その都度いろいろ学ばないといけないことは多い。将来的に誰か専門家を巻き込んでもいいと思うけど、最初は全部自分で経験したほうがいいのかなとは思ってがんばっています。
デザイナーがデザインだけしていると、その業界の中に閉じ込められてなかなか外に広げていけないと思っています。ニューホープ賞の受賞は社会とのつながりが増えるチャンスでもあったし、今後必要なスキルは一つずつ習得していければいいのかなと。
奥村:ちゃんと一つひとつを勉強として考えられていてすばらしい……。
項: 広告を投げてみたところ、最初は全然届かなくて苦労した場面もありました。そのときは所属する会社で広告に詳しい同期に教えてもらったりしました。その過程で勉強になったことのほうが多かったなと思います。
奥村:猪村さんは何か心理的に変わった面はありますか?
猪村:あんまり変わってないかもしれないですね。デザインを専門として学んでいないことも、ある意味強みとして生きているのかなって思います。私が一貫して大事にしているのは、「純度の高い自分でいること」です。
 「アドベンチャーBOX」で遊ぶこどもたちと
「アドベンチャーBOX」で遊ぶこどもたちと
猪村:ひとりでも多くの子どもとご家族に届けたいという思いもあるので、より仕組みに落とし込んでいけるよう思考していきたいと思いつつも、まずは、目の前にいる子どもたちから発せられる力強さや目の輝きにきちんと心を向けて、その子がその子らしく過ごせるようにという願いと共に歩んでいくことを大事にしています。
うまくいくことばかりではないけれども、理想と現実の境界をとかしていく力はデザインが持つ大きな強みだと感じているので、両方の視点を取り入れていきたいと考えています。
奥村:未来を見る視点と目の前のユーザーを見る視点ってすごく重要で、私もそれは行ったり来たりすることが大事なのかなと思います。私たちの活動は社会に新しい価値観をつくろうとしていることだから、すぐに変わるものではないかもしれない。でも、いま届いているユーザーには少しずつ変化が起きているかもしれないから、その母数を少しずつでも増やしていけたらいいなと思います。
項: ユーザーの反応を見ながらブラッシュアップしたり修正したりし続けていくことが大事なのかなと私も思っています。ニューホープ賞の受賞はゴールではなく、社会との接点を持つスタート地点であるということが、改めておふたりの話を聞いていて明確になりました。
焦らずに、自分の考えに向き合ってほしい
――同じ志を持った仲間がいる心強さが伝わってくるお話ばかりでした。2025年度のグッドデザイン・ニューホープ賞が応募受付中なので、最後に、応募しようか迷っている方々にアドバイスやメッセージをお願いできますか。

猪村:評価されるためとか賞を取るためというだけでなく、いまある自分の内側の思いを根っこから問い直し、他者に伝えるきっかけにしてほしいなと思います。一般的なコンペやコンテストって、ある意味「こういうものが望まれるよね」という最適解を目指して自分の思いをそこに収斂させていく部分もあると思うんです。それはニューホープ賞のあるべき姿とはおそらく違うところではないかと感じています。
この賞をいただいたときに、審査委員の方々から根っこにある思いが伝わったとも言ってくださり、審査委員の方々がまっすぐ応募者に向き合ってくださる姿勢に驚いたんです。だからこそ、たとえ受賞にいたらなくても、自分と向き合ったプロセスは将来の糧になると思うので、全力で応募してほしいですね。
私は応募前に審査委員のメッセージを読み込んで想いを受け取り、その想いに答えるよう自分のありのままを綴りました。ある意味このプロセスこそが審査委員との対話でもあると思うので、ぜひこの賞の目指すところを知った上で応募するといいのかなと思います。
項: とても共感します。まず自分が本当にやりたいことをじっくり考えて、それをアウトプットすることが大事かなと思っています。誰かの真似ではなく、いま流行っているからという動機でもなく、自分の文脈でものづくりに取り組んでほしい。そこには必ず価値があると思います。
先ほども話していたように、私たちのようなデザイナーは社会の中で新しい存在なのかなと思っています。そして、毎年新しい受賞者が出ることによって、同じ価値観を持つデザイナーがこれだけいるんだと世の中に伝わっていくきっかけになるはず。
だから、素晴らしい人たちがもっともっとこの賞に応募してきて、みんなで一緒にいいデザインを広めていけたらいいなと思っています。
奥村:おふたりのお話に共感しつつ、あとは「焦らないでいいよ」とも伝えたいですね。学生時代は課題とか賞とかがいっぱいあって進路を考えたりするなかでもクラクラすると思うんですけど、焦って応募するのではなくて自分との対話を一番に大切にしてほしいです。久しぶりに展示会に行ってみるとか、ちょっと本を読んでみるとか、自分に余白をつくりつつ、そこで見えてきたものを表現していくといいのかなと思います!
文:原航平 撮影:井手勇貴 取材・編集:萩原あとり(JDN)
【開催概要】
■「グッドデザイン・ニューホープ賞」公式サイト
https://newhope.g-mark.org/
応募期間:2025年3月25日(火)~8月15日(金)まで
募集内容:応募者が独自に各種専修専門学校・大学・大学院において創作した作品で、2025年10月31日の本賞受賞発表日に公表できるもの
応募資格:個人またはグループとし、2025年4月1日時点で個人またはグループの全員が日本国内の各種専修専門学校・大学・大学院に在籍しているか、2024年6月1日以降に卒業・修了した者
賞:最優秀賞(1点)表彰状、賞金30万円、記念品/優秀賞(7点程度)表彰状、賞金5万円、記念品/入選(点数制限なし)表彰状