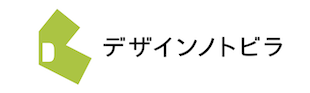東京都立工芸高等学校の教員に聞く。美大・デザイン系学部の入試ってどんな内容?
そもそも私はデザイン系の学部・学科に向いている?
実技を習ったことがなくても受験できるの?
そんな不安を感じながらも、デザイン系の学部や学科へ進学を考え始めた皆さんに向けて、一般大学とは異なる入試の基本的な傾向や対策についてご紹介します。
 手前から、東京都立工芸高等学校のインテリア科主任教諭・竹野秀治先生、教務部主任デザイン科主幹教諭・髙野美歩先生、デザイン科・尾引亮太先生
手前から、東京都立工芸高等学校のインテリア科主任教諭・竹野秀治先生、教務部主任デザイン科主幹教諭・髙野美歩先生、デザイン科・尾引亮太先生
今回、編集部がお話をうかがったのは、これまで多くの生徒をデザイン系の学部・学科に送り出してきた東京都立工芸高等学校の先生方。デザイン系学部・学科の入試の傾向や一般的な大学との入試の違い、面接や実技のポイントなどについて疑問に答えてくれました!
「デザインを学ぶこと」が向いている人とは?
―デザイン系の学部や学科には、具体的にどんな人が向いているのでしょうか?
 尾引亮太先生
尾引亮太先生
尾引亮太先生(以下、尾引):デザインを志す人は、まずは絵を描くことが好き、工作をするのが好き、手を動かすのが好きという生徒が多いですが、上手・下手というより、好きかどうかが大事だと思います。見るだけではなく自分でつくり出していきたい、生み出すことが好きな人。
髙野美歩先生(以下、髙野):自己表現や自己満足、感情を表現する芸術と違って、デザインは誰かのために何かを良くしたい、ちょっと便利にしたい、そういうところに喜びを感じる人が向いているなと感じます。
尾引:そうですね。デザインを本質的に考えると「世の中で機能するもの」だと思うんです。描いたりつくったりしたい気持ちと、世の中で役に立つという部分が繋がっていることが重要です。美術系の大学に行くと、そこを繋げる学びになると思います。
―大学入試を大きく分けると、学力試験が課される「一般選抜」と、書類審査や面接、小論文などで人物を総合的に評価する「学校推薦型選抜」「総合型選抜」の3種類ありますが、そもそも、一般的な大学と美大の入試の違いはあるのでしょうか?
竹野秀治先生(以下、竹野):大きな違いは、美大には実技試験や作品集(ポートフォリオ)の提出があるということですね。これまではそうした実技を重視してきましたが、最近では大学側もいろいろな学生に入学してほしいと考える傾向にあるようです。
総合型選抜や公募推薦、学科のみで入学できる入試もあり、さまざまな経験や価値観を持った学生が入学することで、大学内の活性化が起こることを期待しています。多様な時代といわれているなか、これまでとは違う物差しで学生を募集しているようです。
髙野:今は、6〜7割の生徒が何かしらの推薦を使っていますよね。一般入試までに1〜2回は試験を経験しているので、まずは面接などの対策が先になります。ただ美大などを受験する生徒は国数英理社を軽く見がちなところがある。だからこそ、そこを強みにできたら強いと思います。入学したあとにも必ず必要になりますし、どんな勉強も無駄なものはない。創作活動においても、知っておく方が知らないよりは深いので、勉強もしっかり頑張ってもらいたいです。
―総合大学の工学部のデザイン学科や美大のデザイン学科など、デザイン学科といってもいろいろあります。自分に合った大学や学部に進むにはどう選ぶのが良いでしょうか?
尾引:今は、美大を卒業した人がデザイナーになるという時代でもなくなってきています。美術系や工学系だけでなく、例えば経済学や環境学といった方面からデザインにアプローチしてくる人も。工学系は美的造形力というよりは、設計する技術。ものの性能を上げることを学習します。
美術系はいわゆる美大で、教科でいうと美術や家庭科の延長線。かっこいい、かわいい、おしゃれという感性や情操的な部分で経済に訴えかけるものです。工学系のような性能や技術そのものの向上より、美大のデザインは生活の中での機能美や美しさ、心地よさ、わかりやすさを求めたものが多い。どちらのアプローチが好きかというところから選んでみると良いと思います。
髙野:工学系の場合は、理数科目を履修していないと試験が受けられない大学もあるので、しっかり確認しておくのも大事です。高校の履修にも関わるので美術系か工学系か早めに見極められると安心ですね。
竹野:いま、デザイン系の学部や学科には新しい学びの領域も増えていて、大学によっても学べることがさまざま。将来やりたい仕事について、何のデザインがしたいかを考えて進学先や進路を選ぶのが理想だと思います。
新しい学部・学科が増えているということは、その分野が世の中で必要とされているということだし、人材を育成するために大学も学部や学科を再編しているので、将来を見据えて絞り込んでいくことをおすすめします。
自分の体験や経験を、より具体的に表現することが面接のポイント
―面接ではどんな点がポイントになりますか?
 髙野美歩先生
髙野美歩先生
髙野:最近の高校生は話している内容に実体験、具体例が足りない傾向にあります。具体例がもう少しあるとぐっと真実味が増すと思います。
竹野:そうですね。いろいろと良い体験は持っているんだけど、それを上手に表現できない生徒が多いように思います。もう少し自分を見つめ直して、自分にはこういう経験があるんだ、能力があるんだと、はっきりさせることも大切です。
髙野:具体的なエピソードがあると、「この子が入学したあとどんな動きをするんだろう」「どんな活動をするんだろう」というイメージがしやすいんです。体育祭でどうやってクラスがまとまったのか、どんな問題があったのか、どういう声かけをしたらどう動いたのかなどの具体例を話してもらえると、その生徒の生き生きとした動きが目に浮かびます。
作品の完成に至るまでのプロセスが見えるポートフォリオ
―入試でポートフォリオを提出する場合、どんな点に気をつけると良いですか?
 竹野秀治先生
竹野秀治先生
竹野:ただ完成した作品を見せるだけではなくて、作品の背景や制作過程で生まれた課題、その解決策なども見えるものにするといいと思います。失敗もあっていいし、紆余曲折あって完成した作品のプロセスは見る側も興味があります。
髙野:どんなきっかけでなぜ思いついたのか、アイデアが浮かんだ背景やそのプロセスは知りたいですよね。例えば、完成に行き着くまでのラフスケッチを20個並べるとか。あとは熱量です。どうしてその作品を生み出したのか、失敗談も含めて熱量を持って語ってくれると、より魅力的に見えると思います。
―美大やデザイン系の学部学科を目指したいけど、そもそも実技が苦手という生徒はどうすればいいでしょうか?
尾引:美術系大学では実技試験がないということは少ないですが、最近では実技試験の内容が多様化していて学科ごとに違うことも多いです。昔は指定されたモチーフを鉛筆などで描く「デッサン」や、絵の具を使って形やバランスを見ながら色彩を組み合わせてひとつの画面に仕上げる「平面構成(色彩構成)」、紙やのりなどを使って立体物を造形する「立体構成」などの試験が主流でしたが、課題解決型の入試を行う学校もあるし、みんなでディスカッションしたり、プレゼンテーションしたりする入試もあります。
また事前に映像や動画をつくってそれをアップロードして送るというパターンも。大学や学部によって実技試験の在り方が変わってきているので、まずは調べてみることをおすすめします。
髙野:デッサンや平面構成は、考え方や空間のつくり方、構図の捉え方を身につけることができます。基礎を学んで損はないと思うのでぜひ触れてみて欲しいですね。
尾引:また、デザインの場合は、絵の上手下手より構成力や観察力、それを再現する力が重要になります。これは練習でも十分に身につきますから、苦手意識がある人もまずは挑戦してみて欲しい。ただ自分1人でやっているとわからないし自信もつかないと思うので、わかる人に見てもらったり、アドバイスをもらったりするといいですね。特に初心者の方は伸びるのが早い。すぐに楽しくなると思います。
普通高校では、美術の授業が選択制になっているので、誰に聞けばいいかわからない生徒も多いかもしれません。まずは予備校の春期講習や短期講習に参加してみると良いと思います。予備校も昔は一般入試のデッサンや構成ばかりを教えていましたが、今は推薦入試のためのコースもあります。
髙野:自分がどの位置なのか早めに知るためにも、できれば高校2年生のうちに一度参加してみることをおすすめします。予備校の良いところは、先生だけでなくほかの生徒にも作品を見てもらい切磋琢磨できる点。デザインは人に見てもらってこそなので、見られることに早めに慣れるのは大事だと思います。お互いに見ることで、人の良いところもどんどん吸収できるので、逆にうまく描けない人の方が成長の速度は速いことが多いんですよ。
自分らしい経験や作品で、相手にインパクトを残す
―実技以外で、すぐにできる対策はありますか?

竹野:まずは興味がある大学や学校へ行って先生の話を聞くこと。自分の作品を持って行って見てもらうというのも、印象に残ると思います。特に「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の入試対策で有効だと思います。
髙野:普通高校の生徒はあまりしていないかもしれませんね。都立工芸高校では2年生くらいから行きたい大学の先生とコンタクトを取って、話を聞く機会を持つようにしています。学園祭やオープンキャンパスにも足を運んで、その大学の色を直接見ることは大事です。
だから、試験の時点では先生と何度か面識がある状態が珍しくありません。どんな授業でどんな雰囲気なのか、卒業制作展(卒展)などを見に行って自分の未来のイメージを固めていくことで、入学後のミスマッチを防ぐこともできます。
尾引:大学生が行うインターンシップと一緒で、入試前にすでにいろいろと始まっています。また志望理由や面接で、自分ブランドをどれだけ出せるかというところも重要になります。そのためには高校1年生や2年生の間に、“何か”をやってきていないといけないし、“何か”をつくってきていないといけない。経験や作品をストックするために、とにかくいろいろなことをやっていないといけない。高校3年生になってからアピールするものがない、では遅いんです。
髙野:経験というのは、ものづくりに限らないですよね。例えば旅行に出るのが好きなら、旅行のプランニングをこうやって立てて、こんな風に家族と楽しめたといったような具体的な話をしてくれたら、「行動力があるんだな」と伝わるし。いかに自分らしさ・オリジナリティを出すかが鍵ですね。だから、みんな「自分とは……」ということですごく悩みます。
今後、私たちが戦う相手がAIなどになっていくなかで、1人1人の資質やキャラクターにとても価値が出てくると思います。ただ、AIは今あるものから寄せ集めて素敵なものをつくれるけれど、その事象をつくるのは私たち。新しい分野を切り拓くことはAIにはできないから、新しいものを生み出せる人の力が求められています。
―最後に、デザイン系の学部・学科への進学を考えている高校生へメッセージやアドバイスをお願いします。

髙野:生徒にもよく話していますが、コンテスト情報サイトの「登竜門」などでいろいろコンペに応募して、今のうちから自分の力をどんどん試してみるといいと思います。何か作品をつくるたびにどんどん成長すると思います。
作品づくりをすることで市場調査もしますよね。過去の作品を見たり、ニーズを調査したり、応募要項や企画に合わせてデザインするという大事なことも学ぶことができるのでぜひチャレンジしてみてください。
竹野:ひとつつくるごとにいろいろな情報を自分で集めるようになるし、そうすると街を歩いていても普段なら見えなかった風景が見えてくるんですよね。だんだんとつくり手側の視点になるので、これまで商品しか見てなかった人も、色の配色をみたり、デザインが気になったり。違った見方ができるようになるので、ぜひ自分の作品をつくって挑戦する機会を持ってみてください。
尾引:デザインの仕事は、世の中や隣の人を助けたり楽しませたりするのが仕事。まずは隣の人を楽しませるために何ができるか考えてごらんと、生徒にもよく話すんです。人を楽しませたいという気持ちが、デザインの扉を開く最初の一歩になると思いますよ。
■東京都立工芸高等学校
東京・文京区にある1907年設立の工芸・デザイン系専門高校。これまで工芸作家・デザイナー・アートディレクター・エンジニアをはじめとした多くの卒業生を輩出している。【設置学科】アートクラフト科、マシンクラフト科、インテリア科、グラフィックアーツ科、デザイン科
https://www.metro.ed.jp/kogei-h/
文:高野瞳 撮影:小野奈那子 取材・編集:萩原あとり(JDN)
 手前から、東京都立工芸高等学校のインテリア科主任教諭・竹野秀治先生、教務部主任デザイン科主幹教諭・髙野美歩先生、デザイン科・尾引亮太先生
手前から、東京都立工芸高等学校のインテリア科主任教諭・竹野秀治先生、教務部主任デザイン科主幹教諭・髙野美歩先生、デザイン科・尾引亮太先生