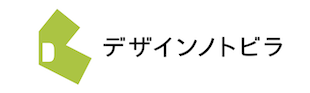世界各国で持続可能な社会づくりが求められている昨今。社会の仕組みや制度のデザインを通して世の中の課題を解決するために、さまざまな活動がおこなわれるようになりました。そういった活動は「ソーシャルデザイン」と呼ばれ、時代の変化とともに需要の高まりが見られます。
なかでも、ソーシャルデザインを教育コンセプトのひとつに掲げる
東京デザインプレックス研究所(以下、TDP)では、学⽣主体のラボラトリー「フューチャーデザインラボ」を企画・運営。「ソーシャル・カルチャー・ビジネス的視点を持つデザイナーを未来に向けて輩出する」ことを⽬的とし、積極的に活動しています。
今回、同校の修了生でデザインを通じて社会課題に向き合うプロジェクトに携わる鴻戸美月さん、水島素美さん、兵藤海さん、藤森晶子さんの4名に、「フューチャーデザインラボ」発のプロジェクトの内容やソーシャルデザインの面白さ、身についたスキルなどについて語っていただきました。
「死生観」「イマジナリーフレンド」「固定種野菜」「医療」……4人が向き合う社会課題とは
――プロジェクトに取り組むことになった経緯についてみなさんにうかがいます。まずは、「さだまらないオバケプロジェクト」のメンバーとして人々の死生観をデザインの力で変えていく活動をしている鴻戸さん、いかがでしょうか。
鴻戸美月さん(以下、鴻戸):TDPに入学し、同校が運営する「フューチャーデザインラボ」に所属したことがプロジェクト発足のきっかけです。
 前職はアパレル会社に勤務していた鴻戸さん。2019年4月〜9月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講。修了後、フリーランスでデザイン業務をおこないながら「フューチャーデザインラボ」に参加
前職はアパレル会社に勤務していた鴻戸さん。2019年4月〜9月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講。修了後、フリーランスでデザイン業務をおこないながら「フューチャーデザインラボ」に参加
鴻戸:ラボに所属すると数名でチームを組み、取り組みたいテーマについて話し合います。私が世の中の死生観に興味を持つようになったのは、TDPスタッフの方がお母様を亡くされ、遺品を捨てられないと話していたのがきっかけでした。
現代の日本では「死」について語ることはあまり好ましく思われません。そのため、悲しみを一人で抱えて塞ぎ込んでしまう。これは誰もがいつか必ず直面する問題です。だからこそ、私たちは「死」の捉え方をデザインの力で変えていきたいと思いました。遺された人が、亡くなった人との思い出を生きる糧にできるような世の中にしようと、さまざまな製品を開発しています。
 共通の故人を知る人同士で集まり、故人の思い出を語り合いながら振り返るきっかけをつくるカードゲーム「ソラがハレるまで」。死別によって心に抱えたモヤモヤとした気持ちを発散し、もう一度故人との素敵な思い出と出会ってほしいという思いが込められている
共通の故人を知る人同士で集まり、故人の思い出を語り合いながら振り返るきっかけをつくるカードゲーム「ソラがハレるまで」。死別によって心に抱えたモヤモヤとした気持ちを発散し、もう一度故人との素敵な思い出と出会ってほしいという思いが込められている
――水島さんも鴻戸さんと同じく「フューチャーデザインラボ」に所属しているんですよね?
水島素美さん(以下、水島):本業である経営企画の仕事をする中で、思考が凝り固まっていることに気づき、新しい視点や発想力を身につけるためにTDPでの学び直しを決めました。特に「フューチャーデザインラボ」は未来を予測しながら課題を発見しアプローチするという点で、本業にも学びが活かせそうだと思い参加しました。
 アパレルブランドの経営企画として働いている水島さん。2019年10月〜2020年6月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講し、フューチャーデザインラボの第4期生として活動している
アパレルブランドの経営企画として働いている水島さん。2019年10月〜2020年6月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講し、フューチャーデザインラボの第4期生として活動している
――水島さんは、大人の発想力を高める「オルタナフレンドプロジェクト」のメンバーですが、「オルタナフレンド」とはなんなのでしょう?
水島:一言で表すと「大人版イマジナリーフレンド※」です。子供の豊かな発想力によって生み出されるイマジナリーフレンドは、年齢が上がるにつれて消えてしまいます。それなのに、発想力は大人になっても求められる。
私自身、本業やラボの活動で、アイデアが思うように出てこなくてやきもきする経験を幾度となくしてきました。そんな中で、イマジナリーフレンドが認知科学の観点で発想力を高める存在として有効だという論文を見つけて、私たち大人に必要なのは発想を手助けしてくれる相棒だと思ったんです。本プロジェクトではワークショップなどを通じて、その相棒として私たちが考えた「オルタナフレンド」を見つける活動をしています。
※「イマジナリーフレンド」とは、通常幼少期に見られる「空想上の友人」のこと。発達心理学などで用いられる言葉
 コミュニティスペース「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」にて、未知の価値に挑戦するプロジェクトとして参加したオルタナフレンドの展示風景。そのほか、日本最大級の科学と社会をつなぐオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」などでワークショップを実施
コミュニティスペース「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」にて、未知の価値に挑戦するプロジェクトとして参加したオルタナフレンドの展示風景。そのほか、日本最大級の科学と社会をつなぐオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」などでワークショップを実施
――現在Web制作会社でデザイナーを本業としている兵藤さんも「フューチャーデザインラボ」所属ですが、ソーシャルデザインに興味を持ったきっかけを教えてください。
兵藤海さん(以下、兵藤):TDPのティーチングアシスタントがこのラボを薦めてくれたことが、きっかけでした。もともと自分が本業で培ってきたデザインのスキルを社会に活かしたいという思いが強く、当時コロナ禍だったこともあって何か世の中に貢献したいと感じていたんです。そんな時にラボの存在を知り、これは挑戦しないと後悔するなと応募を決めました。
 UIデザイナーを経て、現在Web制作会社でデザイナー兼ディレクターとして働いている兵藤さん。2022年1月〜2022年9月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講し、フューチャーデザインラボ第5期生として活動
UIデザイナーを経て、現在Web制作会社でデザイナー兼ディレクターとして働いている兵藤さん。2022年1月〜2022年9月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講し、フューチャーデザインラボ第5期生として活動
――兵藤さんは絶滅の恐れがある固定種野菜を持続させるためのプロジェクトのメンバーですが、固定種野菜とはどんな野菜なのでしょうか?
兵藤:固定種野菜とは、スーパーなどでほとんど出回ることのない、人が手を加えることで何世代にもわたり特性が受け継がれている野菜のことです。これらの野菜は、収穫量が少ないことや外食産業の普及などを理由に生産農家が減り、現在絶滅の危機に直面しています。
その現状を知った私たちはフィールドワークとして各地の農家をまわり、固定種野菜の現状について調べていきました。拾い上げた課題をもとにシェフとコラボした試食イベントを開催するなど、固定種野菜の魅力を知ってもらい、ファンを増やす活動をおこなっています。
 固定種野菜が持続するためのサイクルを「知る・興味→体験→拡散→再購入・新規購入者の獲得→需要増加→生産者増加」と考え、このうち「体験」を提供するイベントを実施。イタリアンレストランのシェフがこの日のために開発した特別メニューを振るまった
固定種野菜が持続するためのサイクルを「知る・興味→体験→拡散→再購入・新規購入者の獲得→需要増加→生産者増加」と考え、このうち「体験」を提供するイベントを実施。イタリアンレストランのシェフがこの日のために開発した特別メニューを振るまった
――続いて、ストーマ(人工肛門)を手術で造設した患者さんの生活を豊かにするための「ストーマパウチプロジェクト」のメンバーである藤森さん。お三方とは違う経緯でプロジェクトに参加されたんですよね?
藤森晶子さん(以下、藤森):私は横浜市立大学先端医科学研究センターのコミュニケーション・デザイン・センターで、医療現場の課題をデザインの力で解決する仕事をしています。本プロジェクトは、ストーマ(人工肛門)を手術で造設した方が排泄物をためておく透明のパウチ(袋)に貼る、デザインステッカーの開発プロジェクトです。患者さんの気持ちを少しでも明るくしたいという大腸外科医の先生の想いから誕生しました。
デザインが肝となるプロジェクトなので、ソーシャルデザイン分野で横浜市立大学と長年交流のあるTDPと共同で活動をスタート。本学とTDPの架け橋役として、TDP出身で本学のデザインセンターで働く私が発足メンバーに加わりました。
 横浜市立大学先端医科学研究センターのコミュニケーション・デザイン・センターのデザイナーとして働く藤森さん。2017年7月〜11月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講し、修了後「ストリートメディカルスクール(TDPと横浜市立大学との協働カリキュラム。TDPの修了生と医療関係者が集い、デザインや医療のプロフェッショナルに学ぶ教育プログラム)」の1期生に。プログラム修了後も2期生のアドバイザーを務める
横浜市立大学先端医科学研究センターのコミュニケーション・デザイン・センターのデザイナーとして働く藤森さん。2017年7月〜11月にTDPのグラフィック/DTP専攻を受講し、修了後「ストリートメディカルスクール(TDPと横浜市立大学との協働カリキュラム。TDPの修了生と医療関係者が集い、デザインや医療のプロフェッショナルに学ぶ教育プログラム)」の1期生に。プログラム修了後も2期生のアドバイザーを務める
――医療分野の課題をデザインで解決するにあたって、どのようなことが大変でしたか?
藤森:私たちがデザインしているのは、透明で中身が確認しやすいという医療側のメリットに特化したストーマパウチを、患者さんの好みや気持ちに寄り添ってアレンジするためのステッカーです。しかし、それは機能上なくても問題ないもの。だからこそ、患者さんが使用中に邪魔に感じたり、不具合が起きたりするようなことは決してあってはなりません。ステッカーのグラフィックをデザインして終わりというわけではなく、医療の観点からも使用して問題がないかを細かく検証していく必要があります。
 ストーマパウチのステッカーデザインはTDPの学生たちが担当。藤森さんはそれらの取りまとめやステッカーカタログのデザインのほか、クラウドファンディングの運営、ストーマパウチメーカーや印刷会社とのやりとり、納品までのディレクションを担当している
ストーマパウチのステッカーデザインはTDPの学生たちが担当。藤森さんはそれらの取りまとめやステッカーカタログのデザインのほか、クラウドファンディングの運営、ストーマパウチメーカーや印刷会社とのやりとり、納品までのディレクションを担当している
完成までは試行錯誤の繰り返しでしたが、先生やストーマパウチメーカー、印刷会社などあらゆる分野のプロの方たちの協力のもと、ステッカーを無事患者さんに届けることができました。大変なことも多かったですが、使っていただいた方から喜びの声をいただいた時は、心からつくって良かったと思いましたね。
デザインとは、自分の気づきを形にする力
――プロジェクトに取り組んだからこそ得られた学びや身についたスキルはありますか?
鴻戸:学生としてデザインを勉強していた時は、自分が身につけた制作スキルで何ができるのか、よくわかっていませんでした。しかし、プロジェクト活動の中で、自分たちで問題を発見し、深掘りし、アイデアを形にするまでやり通す力が身についたと感じています。「デザイン」とは、こうなったらよいと思ったことを自分の手で実現させる力でもあるんだと、身に染みて実感しました。
――ソーシャルデザインの対象となる社会課題の中には、鴻戸さんが向き合っている「死」の問題も含まれているのですね。
鴻戸:私たちは、課題をデザインで解決したいというより、課題についてみんなが考えるきっかけをつくりたいと考えています。「私たちはこう思うんです!」と信念をぶつける活動ではなく、「こういう考え方をしてみてはどうだろう?」と優しいコミュニケーションをしていきたい。そういういろんなコミュニケーションを生み出すことができるのもデザインの魅力の一つだと思います。

違和感と向き合いつづけることが大事
――ソーシャルデザインに携わる上で大事なことを教えてください。
兵藤:ソーシャルデザインの活動では、自分の気持ちや違和感を大事にすることがすごく大切だと思います。自分たちが提起した問題に対して、本気で解決したいという想いが、人々に共感されるデザインを生み出します。もし日常にちょっとした違和感を覚えているなら、その感覚を大事にしながら、いろんなソーシャルデザインの事例を調べてみるのもいいかもしれません。
水島:仕事をしていると自分では違和感があっても、それを受け入れるのが大人だという価値観が当たり前になりがちです。私もそうでした。しかし、ラボでの活動を通して世の中の当たり前に対して「本当にそうなのか?」と自分で問いを立てる力が身につきました。デザインの領域は目に見えるものだけでなく、課題提起や戦略、コンセプトなど目に見えない部分まで広がっています。特にソーシャルデザインはその目に見えない部分を考え抜く力が試される分野です。そういった思考力を身につけたい人にとっては最高のフィールドだと思います!

アイデアを形にすることから始めてみてほしい
――最後に、デザイン分野に興味を持っている読者のみなさんにメッセージをお願いします!
藤森:ソーシャルデザインに取り組む中での一番のやりがいは、自分の頭の中のものを社会に役立つ形で具現化できることです。口頭だけのアイデアや実現性のないイメージでとどまっていたものを最後までつくり切ることは、自信にもつながります。もちろんつくってみて初めてわかる自分の至らなさもたくさんあります。だけど、より良いものをつくるために、頭の中だけで終わらせずに、とにかくスケッチや模型など自分の手でつくってみることを大事にしてほしいです。そういった機会がTDPには豊富にあるので、デザインに少しでも興味のある方はぜひチャレンジしてほしいと思います!
取材・文:濱田あゆみ(ランニングホームラン) 撮影:加藤雄太 編集:萩原あとり(JDN)