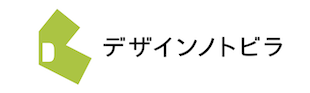デザイナーになりたい。だけど、どんなステップを踏めば良いのかわからない。そんな方にとって「デザイン学校」と「デザインコンペ」は理想を叶える手段になるかもしれません。学校で身につけた知識やスキルを、デザインコンペを通して実績に変える。新たなキャリアを切り拓くカギが、好きなことを仕事につなげる「デザイン学校」と「コンペ」に隠されています。
今回は、デザインノトビラとコンテスト情報サイト「登竜門」の連動企画。実践的に学べるデザイン専門校「東京デザインプレックス研究所(以下、TDP)」を卒業し、デザインコンペ受賞の実績を活かしてデザイナーへの転身に挑む増谷誠志郎さん(以下、増谷)と髙田夏希さん(以下、髙田)にお話を伺いました。
「デザインノトビラ」では、学校での学びを中心にご紹介します。
【「コンペ編 by 登竜門」はこちら!】
新たなチャレンジを、東京デザインプレックス研究所で。
― 増谷さんは社会人を4年間経験した後、髙田さんは大学休学後にTDPに入学されているとのことですが、入学前はどんなことをしていたのですか?
増谷:もともとものづくりが好きで、自動車部品メーカーでエンジン部品の開発に携わっていました。そんな中で、4年目には自分がやりたかったことは一通り経験できたと感じるようになって。そこで改めて「自分が今一番やりたいことって?」と考えた時に、学生時代から興味があったデザインが思い浮かんだんです。
でも、当時の僕にはデザインに関する知識は何もなかったので基礎から学ぼうと、デザイン系の学校を探し始めました。
 増谷誠志郎(ますたにせいしろう) 自動車部品メーカーに4年間在籍後、東京デザインプレックス研究所 デジタルコミュニケーションデザイン専攻に入学、2020年3月修了。同年9月に友人と「SANAGI design studio」を設立。代表作は、2020年度 東京ビジネスデザインアワードの最優秀賞提案であり後に商品化した「さかなかるた」で、2022年グッドデザイン賞(グッドデザインベスト100、グッドフォーカス賞)も受賞している。2021年度 東京ビジネスデザインアワードでも優秀賞など3つの賞を獲得。
増谷誠志郎(ますたにせいしろう) 自動車部品メーカーに4年間在籍後、東京デザインプレックス研究所 デジタルコミュニケーションデザイン専攻に入学、2020年3月修了。同年9月に友人と「SANAGI design studio」を設立。代表作は、2020年度 東京ビジネスデザインアワードの最優秀賞提案であり後に商品化した「さかなかるた」で、2022年グッドデザイン賞(グッドデザインベスト100、グッドフォーカス賞)も受賞している。2021年度 東京ビジネスデザインアワードでも優秀賞など3つの賞を獲得。
― デザインとは全く異なる分野からのチャレンジだったのですね。髙田さんはいかがですか?
髙田:私は大学で演劇を学びながら、役者を目指してオーディションや舞台の稽古に明け暮れていました。しかし、舞台活動に打ち込むと大学に通う時間がない。まずは自分がやりたいことに向き合おうと、2年生の時に大学を休学することにしました。
デザインの仕事に興味を持ち始めたのは、音楽活動をしている知り合いのCDジャケット制作がきっかけでした。私が以前から趣味でイラストを描いていることを知って、依頼してくれたんです。それから、演劇をしながらデザイン制作活動もするようになりました。
 髙田夏希(たかた なつき) 大学で演劇を専攻した後、東京デザインプレックス研究所 デジタルコミュニケーションデザイン専攻に入学、2022年3月に修了。同校講師アシスタントを務め、現在はフリーランスのデザイナーとして活躍中。「デザインで演劇を盛り上げる」という目標に向けて制作活動を行う。「JAGDA国際学生ポスターアワード2022」金賞受賞。
髙田夏希(たかた なつき) 大学で演劇を専攻した後、東京デザインプレックス研究所 デジタルコミュニケーションデザイン専攻に入学、2022年3月に修了。同校講師アシスタントを務め、現在はフリーランスのデザイナーとして活躍中。「デザインで演劇を盛り上げる」という目標に向けて制作活動を行う。「JAGDA国際学生ポスターアワード2022」金賞受賞。
― デザイン系の学校への入学を決めた理由はなんだったのでしょうか?
髙田:演劇もデザインも本当に楽しくて、両方続けていきたかったのですが、現実的にお金を稼ぐことを考えて、デザインスキルを磨いていこうと、デザイン学校への入学を決めました。
個性豊かで熱量の高い生徒に囲まれた、刺激的な学校生活。
― 多くのデザイン系専門学校がある中で、TDPを選んだ決め手を教えてください。
増谷:僕はとにかく早くスキルを身につけたいという想いがありました。だから、1年制で短期間、かつ実践的な授業が多かったTDPが一番魅力に感じたんです。エンジン部品開発に携わっていた時から「やりながら覚えていくこと」を大事にしていたので、学び方のスタイルも自分に合っていると思いましたね。
髙田:私も増谷さんと同じ理由でしたね。実践的な授業でいうと、たとえば広告やパッケージ、Webサイト制作など実際に作品をつくる授業だけでなく、デザインの目的から組み立てるブランディングの授業などがありました。デザインの仕事に必要な工程を一から学ぶことができるので、デザイナーに必要なスキルが身につくと思ったんです。
― 実際にTDPに通い始めた時の心境はいかがでしたか?
増谷:「想像以上にいろんな人がいるんだなあ」と驚きの連続でした(笑)。僕と同じように仕事をやめて入学した人も多く、それぞれが違った専門性を持っていて、本当に刺激になりましたね。牛への愛をひたすら語る農協出身のクラスメイトもいて、今でも強烈に覚えています(笑)。

髙田:私のクラスも個性的な人が多かったです!だけど、デザインに関してはみんな初心者。だからこそ、クラスメイトの成長がそのまま自分への刺激になるんです。1年という限られた時間だからこそ、「絶対にこの間に学びきろう!」という意欲をみんな持っている。とにかくみんなの士気が常に高い環境でしたね。
 授業風景
授業風景
デザインそのものの考え方が、今の仕事にも生きている。
― 学校生活についてお伺いしましたが、TDPで学んだことの中で、今の仕事に活きていることを教えてください。
増谷:やはり実践的なスキルが学べたのはとても大きかったように思います。特に「プレックスプログラム」という各業界のトップクリエイターが登壇するワークショップでは、実際の案件をベースにしたワークを通して、デザインにおける根本的な考え方を学ぶことができました。
 「プレックスプログラム」のワークショップの様子
「プレックスプログラム」のワークショップの様子
入学前の僕は、デザインとはかっこいいモノをつくることだと思っていました。しかし、ワークショップでロゴ制作や商品企画をしていると、むしろ見た目以外の部分の考察が大切だと身にしみてわかってくるんです。まず目的やターゲットをしっかり考え抜くこと。デザインを機能させるために、この考えはデザイナーとしてずっと大事にしています。
― 増谷さんは卒業後デザインコンペ『東京ビジネスデザインアワード』で最優秀賞を獲得していますが、応募作品を制作する際にも、デザインの目的やターゲットから向き合うという考え方を大事にしていたのでしょうか?
増谷:そうですね。僕は42億色を表現できる印刷技術を持った企業の課題を解決するために、「さかなかるた」というプロダクトを考案しました。このプロダクトを制作する時に一番大事にしたのは「その企業が持つ技術力を活かしながら、看板商品となる新たな収益源をつくる」という目的。そのために、「企業内で制作を完結できるか」ということをかなり意識してデザインしました。
 2020年度東京ビジネスデザインアワード最優秀賞・2022年度グッドデザイン賞「さかなかるた」
2020年度東京ビジネスデザインアワード最優秀賞・2022年度グッドデザイン賞「さかなかるた」
金賞獲得のカギは、さまざまな人の目線を取り入れたこと。
― 髙田さんも卒業後に『JAGDA国際学生ポスターアワード2022』で金賞を受賞しています。どんなことを意識しながら制作していたのでしょうか?
髙田: この作品は、自分が当事者であることと、配置するもの全てに意図を持たせることを意識しながら制作しました。あと、たくさんの人に意見を聞きました。作品に対して意見を聞くことに苦手意識があったのですが、この作品では初めて素直に意見を聞けました。皆さまざまな好みがある中、汲み取りたいところを汲み取って、自分に響かない意見は反映させない、という判断ができたのは大きかったと思います。
 JAGDA国際学生ポスターアワード2022 金賞「ILY」
JAGDA国際学生ポスターアワード2022 金賞「ILY」
デザインコンペへの挑戦について、詳しくは「コンペ編 by 登竜門」へ!
「迷ったらGO!」道筋は入学してから見つかる。
― 最後に、TDPに興味を持っている方や入学を検討している方に向けて、メッセージをお願いします!

髙田:TDPは課題も多く大変なことはたくさんありますが、1年しかないからこそ、途中でだらけることなく学業に専念できる学校です。また、グラフィックもWebも両方学べるカリキュラムなので、デザイナーとして様々な武器が身につけられる。私自身、グラフィックの仕事を中心にやりつつ、Webデザインの仕事も受注したりと、幅広い業務に携わることができています。
とにかく私から言いたいのは「迷ったらGO!進んでほしい」ということです!今は目標ややりたいことがはっきりしていなくても、TDPに通っている中で道筋が見えてきます。

増谷:やる気次第でどうにでもなるので、難しいことは考えずに「デザインを学びたい」と思ったらまっすぐ突き進んでみてほしいと思います。髙田さんも言っていましたが、具体的なことは入ってみてから考えればいいし、TDPはいろんな選択肢が広がっている場所です。「1年で絶対に学びきるぞ!」という気持ちで、なりたい自分に近づいていってほしいですね。

取材・執筆・編集:濱田あゆみ(ランニングホームラン)、撮影:加藤雄太、企画:猪瀬香織(JDN)
※前編はこちら!