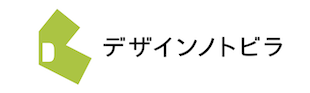武蔵野美術大学での思い出と、デザイナーとしての現在につながる4人の卒業制作とは?
武蔵野美術大学での学生生活
――みなさんは武蔵野美術大学出身ですが、大学選びの決め手は何だったのでしょうか?
沖田颯亜さん(以下、沖田):受験時の第一志望は東京藝術大学で、現役の時は藝大しか受けてなかったんです。浪人時代も第一志望は藝大にしていたんですが、やっぱりすごく大変で、第二志望として武蔵野美術大学を受けました。理由としては、両親がインテリアデザイナーと画家で、ふたりの出身大学だったことが大きいですね。
結局武蔵野美術大学に進学したのですが、私が入学した基礎デザイン学科は、有名なデザイナーの方々が教授を務めていて、そこで学べるのであれば、グラフィックにしろプロダクトにしろ、まだ進路が決まっていなくても卒業後に目指すことができるのがこの学科の魅力だなと感じていました。

沖田颯亜(おきだそうあ)さん
坂本俊太さん(以下、坂本):僕は大阪の吹田市出身なので、家から通える距離の学校を考えて、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)に入学しました。プロダクトやインテリアにも興味があったんですけど、将来のことを考えるとWebの方が道が開けるかなと思い、情報デザイン学科に入りました。
高校まではあまり知識がなかったのですが、大学に入ってからいろいろとデザインの世界が広がっていったんですよね。それこそ、いま僕は広告の会社にいますが、当時はそもそもデザインと広告が関係あるっていうことすらわかってなくて。同じ学科の友だちで、コピーライターになって広告に関わりたいというやつがいたんですけど、「なんで広告やりたいのにデザイン科に来たの?」って思うくらい、その頃は何も知らなくて(笑)。大学に入って本当にいろいろなことがわかっていった感じですね。
 坂本俊太(さかもとしゅんた)さん
坂本俊太(さかもとしゅんた)さん
坂本:そんな中で、2年生のときにグラフィックデザイナーの原研哉*さんの存在を知ったんです。原さんは、デザインだけじゃなく、いろんなプロジェクトの仕事をされていて、「デザインってじっくりと時間をかけて学ぶ価値のあることなんだな」とあらためて感じ、原さんが教えているムサビで学びたいと思うようになりました。僕はデッサンができないんですが、基礎デザイン学科はデッサンなしで編入できるのがよかったですね。
*原研哉(はらけんや):日本デザインセンター代表取締役を務めるグラフィックデザイナー/アートディレクター。無印良品のアートディレクションや、松屋銀座、森ビル、蔦屋書店、GINZA SIX、ヤマト運輸のVIを手がけるほか、展覧会のディレクションや、写真・動画・文・編集を手がけるWebサイト「低空飛行」など、幅広いプロジェクトを手がける。おもな著書に『デザインのデザイン』(岩波書店、2003)、『日本のデザイン』(岩波新書、2011)、『白百』(中央公論新社、2018)など。
山田十維さん(以下、山田):僕は中学卒業後に5年制のデザイン系の高専に入って、3年次からムサビに編入しました。基礎デザイン学科を選んだのは、僕が好きだった「竹尾ペーパーショウ」をディレクションされている原先生が教授をされていたからですね。ちなみに藤谷とは高専から一緒でした。
藤谷力澄さん(以下、藤谷):僕は3人と学科が違って、高専卒業後は武蔵野美術大学の視覚伝達デザイン学科に編入しました。当時は、デザインの仕事に就きたいと思ってはいたものの、分野までは絞り込めていなかったので、イラストやアニメーションなど、幅広く学ぶことができる視デを選びました。
――特に印象的だった授業はありましたか?
沖田:私は2年生の時に受けたプロダクトデザイナーの柴田文江先生の「形態論」がおもしろかったです。たとえば、「速い」と想像できる魚や自動車のフォルムについて考えたりする授業で、自分が「柔らかい」と思うかたちを石膏粘土でつくるという課題が出たんですが、いざ自分が考える柔らかいかたちをつくろうと思っても、なかなか思ったようにきれいなカーブが出せなかったり、すぐにはうまくいかないんですよね。そういった体験を身体に染み込ませる、とてもいい授業だったと思います。
坂本:僕は原先生のヴィジュアルコミュニケーションについての授業ですね。課題のテーマが「カフェ」だったので、「ぴったり100キロカロリーの食べ物しか置いていない店」をコンセプトに、模型からお店のネーミング、ロゴデザイン、書体設計まで、すべてつくったことが印象に残っています。あと、半分は原先生のファンとして受けていたところもあったので、授業でしか見ることができない原先生の仕事の裏側が垣間見れたのも興味深かったですね。
――視覚伝達デザイン学科出身の藤谷さんはいかがですか?
藤谷:僕の学科は、代理店などで活躍されている現役のアートディレクターの方が講師としていらしていたのですが、その方が出す課題を2週間で作品として仕上げて提出する、という授業が印象的でしたね。とても大変でしたが、毎回講評いただけるので本当に身になったと思います。
 藤谷力澄(ふじたにりきと)さん
藤谷力澄(ふじたにりきと)さん
坂本:僕もその授業を取っていたことがあって、その授業がきっかけで就職活動で代理店を目指すようになりました。入学前の美大のイメージでは、ひとつの作品を仕上げるのに2〜3ヶ月ぐらいかけられると思っていたのですが、ムサビは「1週間でアイデアを出してつくってきてください」という授業がすごく多かったんですよね。そのときは「そんなの無理でしょ……」と思ったんですが、苦しみながらもなんとかやってみると、案外できるものだなぁって。実際に社会に出てみるとそんなことばかりなので、いまだにその経験は役に立っているかもしれないですね。
卒業制作として取り組んだ4人の作品
山田:僕が印象に残っていることといえば、やっぱり原先生のゼミですね。よく怒られてましたけどね(笑)。藤谷以外のこの3人は同じ原ゼミの生徒でした。原先生のゼミは特徴的で、はじめにゼミ生がそれぞれ気になる言葉を壁に貼り出して、その中からテーマを決めて作品をつくっていくんです。
 山田十維(やまだとおい)さん
山田十維(やまだとおい)さん
山田:僕たちのときは「生(なま)」というテーマでした。「live」という意味もあるし、生体しての「生」や「生々しい」「新鮮」など、本当に幅広く解釈できるテーマだったので、いろいろなアプローチがしやすかったですね。
僕はこのテーマを、素材としての「生」と捉えて、大量生産・大量消費の象徴としての「缶」を、自分の手で素材に戻していくという過程を卒業制作にしました。コーラなどの空き缶を1,500個集めて、500個は紙やすりで削り、500個は圧縮してリサイクル前の状態である正方形にして、もう500個を溶かした状態にして並べる作品をつくりました。

 素材としての「生」をテーマに制作された山田さんの卒業制作
素材としての「生」をテーマに制作された山田さんの卒業制作
――手を使って素材に戻していくというデザインプロセスには、どのように行き着いたのですか?
山田:作品のテーマをこの方向性にしようと思ったときに、「大量生産」といちばん対極にある「自分」を対比させるのがおもしろいんじゃないかと考えたんです。なので、その後の制作プロセスは結構すんなり決まりました。
――原先生からの評価やフィードバックはいかがでしたか?
山田:正直プレゼンについては緊張していてあまり覚えていないのですが(笑)、最後は褒めてくれましたね。あと印象的だったのが、制作の過程で僕が「これは業者に頼みます」と言ったら、「業者“さん”と言いなさい」と言われたことでした。デザインの仕事は、業者さんを含めてたくさんの人と協働しながら進めるものなので、すべての人にきちんと敬意を持ちなさいということだったんだと思います。ゼミ時代はたくさん怒られましたが、原先生は一人ひとりのことをきちんとみてくれて、途中で脱落しないようにフォローしていただきましたね。
沖田:私の卒業制作は、「違和感から派生したファッション」という切り口の作品でした。アートディレクターとして制作できるような作品をつくりたいと思っていたので、フォトグラファーやモデルさんと一緒にビジュアルを制作することは先に決めていました。この作品では、ラップユニット「chelmico」のRachelちゃんにモデルをしていただいています。
私は「生」というテーマを解釈するにあたって、「生きていると実感するのはどんな時だろう」と考えて、傷ついた時に、SOSとして痛みを感じることもその証のひとつだなと思い、「傷口」を作品のモチーフにしました。その時に、人間が生まれてから最初にできる傷口って、へその緒だなと思ったんです。
そこで、おへそや耳の穴などに包帯を巻くことで、人は違和感を感じるんだろうか? と考え、その違和感をビジュアル化した作品をつくりました。さらに、人間だけじゃなくて、ペットボトルや絵の具に絆創膏を巻くことで「もの」の傷を表現したり、靴やネックレス、チョーカーなどに傷口をつくることで、違和感をファッションに落とし込んだビジュアルを制作して、マガジンとしてまとめました。
 「傷口」をモチーフとした沖田さんの卒業制作
「傷口」をモチーフとした沖田さんの卒業制作坂本:僕は、一見「生」というテーマから遠いデジタルの情報に結びつけられないかなと考えて、聴診器で聞こえる自分の「心音」の周波数やリズムを、グラフィックパターンに変換してテキスタイルをデザインする装置をつくりました。心音って、自分ではコントロールできないですし、実はすごく「live」なデジタル情報だなと思ったんです。
最初は心音を使ってシンフォニーみたいな音楽をつくることを考えていたんですが、聴診器を買ってみてゼミに持っていった時に、聴診器でみんなの心音を聞いていくと、「一人ひとり心音って違うんだな」ということに気づいて。単純に、ゼミのみんなが楽しそうに反応してくれるのもうれしかったですし、原ゼミの過去の作品は、詩的で彫刻的なものが多かったので、こういったみんなが盛り上がる作品をつくれば、ちょっと目立てるかなという気持ちもありましたね。
そこから、個性を表すものとしてのファッションを連想して、心音をテキスタイルに落とし込む作品にしようと考えました。「MAX/MSP」という音楽のプログラミングにも使用されるソフトで制作しているのですが、僕はもともと音楽をつくったり、Webサイトを自分でつくることからデザインに触れるようになったので、この作品では、そういったいままで片足を突っ込んできた要素をうまく集めることができてよかったなと思っています。
 坂本さんの卒業制作「Pattern Per Heart」のビジュアル
坂本さんの卒業制作「Pattern Per Heart」のビジュアル

坂本さんの卒業制作の展示風景
――藤谷さんは視覚伝達デザイン科でどなたのゼミに所属されていたんですか?
藤谷:僕は新島実先生のゼミに所属していました。卒業制作に関しては、自分の気になることややりたいことを新島先生と面談しながら掘り下げつつ、最終的なテーマを決めて作品づくりにつなげるという流れでした。
僕は、当時までの22年間で通ったことのある道をテーマに考えていて、たとえば通学路や友だちと出かけた時に通った道など、ケータイの画像やカレンダーからデータを抽出して、すべての歩行路を地図上にマッピングした映像作品を制作しました。
単純に、自分がこの作品を通して視覚化して見てみたいなと思ったのが動機なのですが、これまでに歩いたことのある道だけを抽出することで、「自分が知っている世界ってこれだけなんだ」ということがわかるというか、自分の知っていることと知らないことが可視化されるような作品になるんじゃないかなと思ったんですね。僕は着実に何か一つをつくり上げることが好きなタイプなので、振り返ってみるとこの卒業制作のテーマにも表れていたと思いますし、いまの仕事への向き合い方も同じだなと感じています。