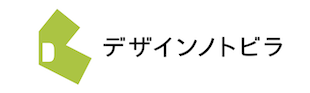コラム
多摩美術大学
【2024年10月・11月開催】美術系大学・学校のセンスが光る!学園祭ポスターまとめ
美大・デザイン系の学校の学園祭日程は、デザインノトビラ「イベントをさがす」ページから検索できます。ぜひ活用してみてくださいね!注目の学園祭ポスターを編集部がピックアップ!学年や学科・学びの領域を飛び越え、学生たちがつくり上げる学園祭。とくに美大・デザイン系の学校においては、学生の創造力が存分に発揮される一大イベントです。進学を考えているなら、志望校の色を知るためにも訪れない手はありません!本コラムでは、そんな学園祭の楽しさや魅力を伝えるポスターに注目。2024年10月・11月に開催される学園祭のなかから、デザインノトビラ編集部がピックアップしたポスタービジュアルを、開催情報とともにご紹介します。センスの光るポスターがこちら!女子美術大学「女子美祭2024」(杉並キャンパス・相模原キャンパス)【杉並キャンパス開催情報】テーマ:「CIRCUS!」日時:2024年10月25日(金)~27日(日)/10:00~18:00(作品展示17:00まで)場所:女子美術大学杉並キャンパス(東京都杉並区和田1-49-8)アクセス:東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」より徒歩約8分【相模原キャンパス開催情報】テーマ:「舞踏会」日時:2024年10月25日(金)~27日(日)/10:00~17:00(作品展示16:30まで)場所:女子美術大学相模原キャンパス(神奈川県相模原市南区麻溝台1900)アクセス:小田急線「相模大野駅」下車、北口バス乗り場「女子美術大学」行きバスで約30分/JR横浜線「古淵駅」下車、駅前2番乗り場「女子美術大学」行きバスで約20分武蔵野美術大学 芸術祭2024「海底王国MAUREEF」【開催情報】テーマ:「サンゴ礁」日時:2024年10月25日(金)~27日(日)/10:00~18:00 ※最終日18:30(最終入場 25,26日 17:30、27日 18:00)場所:武蔵野美術大学鷹の台キャンパス(東京都小平市小川町1丁目736)アクセス:西武国分寺線「鷹の台駅」下車、徒歩18分/JR中央線「国分寺駅」北口下車「国分寺駅北口」4番停留所より西武バス「武蔵野美術大学」行または「小平営業所」行に乗車、「武蔵野美術大学正門」停留所下車すぐ倉敷芸術科学大学 第30回「芸科祭」【開催情報】テーマ:「溢(いつ)」日時:10月26日(土)・27日(日)場所:倉敷芸術科学大学(岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地)アクセス:JR「新倉敷駅」よりバスで約12分京都芸術大学「大瓜生山祭 2024」【開催情報】テーマ:「火花」日時:11月2日(土)・3日(日)/10:00~17:00場所:京都芸術大学瓜生山キャンパス(京都市左京区北白川瓜生山2-116)アクセス:地下鉄「北大路駅」より市バス204系統循環 銀閣寺方面「上終町・⽠⽣⼭学園 京都芸術⼤学前」下車(所要時間約15分)/京阪「出町柳駅」より市バス上終町3系統 上終町・⽠⽣⼭学園 京都芸術⼤学前行「上終町・⽠⽣⼭学園 京都芸術⼤学前」下車(所要時間約15分)多摩美術大学芸術祭2024 in 八王子キャンパス【開催情報】テーマ:「Tamability」日時:2024年11月2日(土)~4日(月)/10:30~18:00(展示 10:30~17:00、模擬店 10:30~、フリマ 10:30~16:30)※催し事により終了時刻は異なる。予定は変更することあり場所:多摩美術大学八王子キャンパス(東京都八王子市鑓水2-1723)アクセス:JR横浜線・京王相模原線「橋本駅」北口から神奈川中央交通バス「多摩美術大学行」で約8分/JR「八王子駅」南口から京王バスで約20分文化学園大学 第74回 文化祭「B-LIGHT」【開催情報】テーマ:「B-LIGHT(ビーライト)」日時:2024年11月2日(土)~4日(月・振休)/9:30~17:00(最終日は~16:00)場所:文化学園大学(東京都渋谷区代々木3-22-1)アクセス:JR「新宿駅」南口または「甲州街道改札」より甲州街道に沿って初台方面へ徒歩7分筑波大学 芸術専門学群「芸術祭2024」【開催情報】テーマ:「爆゛」日時:2024年11月3日(日)〜4日(月・振休)場所:筑波大学6A棟、6B棟、5C棟2階(茨城県つくば市天王台1丁目1-1)アクセス:つくばエクスプレス(TX)「つくば駅」隣接のバスターミナル「つくばセンター」よりバスで15~20分学園祭を調べよう!いかがでしたか?各学校の学園祭については「イベントをさがす」ページから検索できます。ぜひ活用してみてくださいね!
2024年10月18日(金)