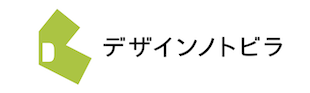フリップ・フラップ
[最優秀賞]
脳が操作する以上、言語で描く対象はすべて予定調和になりがちだ。
「Aさんはご飯を食べた」。「Bさんは卵焼きを焼いた」etc…。まるで脳の指令を身体がなぞって、行為が順当に完成・完結しているかのごとくではないか。
本作品はメンタルを病んだ主人公が通行人カウントのアルバイト体験を通して、回復のきっかけをつかむ有様を描いているのだが、圧倒的な現実の手触りが伝わってくる。人間の動作はあらかじめ脳が中央集権的に決定しているわけではなく、手や足などの身体自体が脳とは独立し、不測の事態と偶然性に満ちた環境と試行錯誤しながら折り合いをつけていくプロセスだ。
本作品において登場人物たちは、動作レベルでの細やかな偶然性(例・P28)からはじまり、不審者がやって来るのか来ないのかという事件レベルでの運命的な偶然性(例・P58)まで、さまざまなレベルの偶然性と折り合いつつ生きている。偶然についての文体と物語とのこうした一致が、独特のリアリティに繋がっていることはいうまでもないだろう。
- 卒業年度
- 2022年度