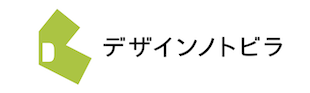Graph Jockey
『Graph Jockey』はレコードを擦って曲をミックスする行為から着想を得た、グラフの時間を操作しながら情報の比較ができるインターフェイスの提案です。
DJは曲をミックスするときにレコードを擦って、曲の時間(速さ)を伸ばしたり、縮めたりすることでテンポを揃えて綺麗に2つの曲をミックスしています。この曲をミックスしていく仕組みを「グラフ」に置き換え、2つのグラフをミックスし、時間を操作することで情報の類似点を発見できると考えました。
Graph Jockeyは、レコードを擦ることでグラフの波形を伸縮しながら情報の比較ができます。それにより期間のズレや異なる期間同士のグラフの類似点を発見することが可能になります。また、様々なデータの中から自分が比較したいグラフを選択し比較することで、意外な情報の類似点といった、操作することでしか得られない新しい相関、因果関係を発見できるのがGraph Jockeyの特徴です。グラフが類似した時には、音楽がなることで感覚的に類似したことを知らせてくれます。
この作品を通してあなたもGJになりませんか?
- 卒業年度
- 2021年度